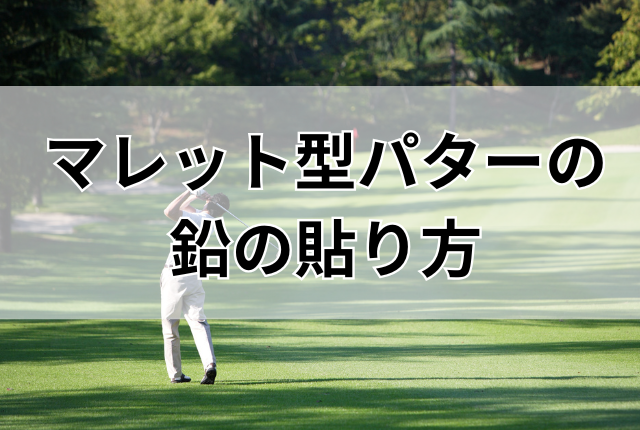※この記事はプロモーションを含みます
ゴルフのスコアを左右するパッティング。
その精度を高めるために、多くのゴルファーが行っているのが「パターに鉛を貼る」調整です。
特にマレット型パターは、ソール面が広く、鉛の貼り方ひとつで打感・方向性・振りやすさが大きく変わります。
「引っ掛けを防ぎたい」「真っ直ぐ打ちたい」「重さを感じたい」──そんな悩みを、鉛の貼り方で解決できるかもしれません。
本記事では、マレット型パターを対象に、鉛の効果的な貼り方から失敗例、プロの活用法まで徹底解説します。
初めて鉛調整にトライする方でも実践できるよう、写真やアイテム例も交えてわかりやすく紹介します。
Contents
- 1 【マレット型パターの特徴と鉛の効果】
- 2 マレットパターに鉛を貼る前に知っておくべきこと
- 3 【基本編】マレット型パターの鉛の貼り方と位置のコツ
- 4 パターに鉛を貼るのはルール違反?知っておきたい規則と注意点
- 5 【比較】ピン型・2ボールパターとの鉛の貼り方の違い
- 6 【プロ実践】ツアープロはパターに鉛をどう貼っているのか?
- 7 パターの鉛で「引っ掛け」や「右に出る」悩みは改善できる?
- 8 【実践レビュー】シャフトに鉛を貼った場合の変化とは?
- 9 【鉛の重さ選び|「何グラム」が適量なのか?】
- 10 おすすめの鉛シート・パター用ウェイトアイテム
- 11 【まとめ】鉛の貼り方でマレットパターの性能は激変する!
- 12 ✅【記事まとめ】
- 13 【PR】気づいた人から使っている!しゅうごる部で話題沸騰中の人気ゴルフアイテム
- 13.1 自宅で距離感を鍛えるパターマット|プレミアムプレッシャートレーナー
- 13.2 ショートパットを徹底的に安定させたい方へ|SUPER-BENT スーパーベントパターマット
- 13.3 自宅で本格スイング練習ができる大型スイングマット
- 13.4 冬ゴルフでも冷えに負けないハンドウォーマー付き防寒グローブ
- 13.5 風を防いで快適にプレーできる ピンの長袖ウインドブレーカー
- 13.6 眠っていた代謝を呼び覚ますヒートラップ
- 13.7 ゴルファーの毎日を支える24時間リカバリーウェア ReD
- 13.8 プロや上級者も注目!体の軸を支えるコアフォース
- 13.9 軽さと収納力を両立した 8本収納ゴルフバッグ パイクスピーク
- 13.10 ミニマルデザインで差がつく 9インチスタンドキャディバッグ
- 13.11 大人ゴルファーのための限定キャディバッグ
- 13.12 上質感のあるデザインで、ゴルフ場でも大人らしい雰囲気を演出したい方に
- 13.13 初心者も安心 バッグが選べるワールドイーグル14点フルセット
- 14 高初速と直進性を両立する Qi35 ドライバー
- 15 しゅうごる部の皆はどうしてる?単発レッスンはまず口コミをチェック
- 16 ゴルフ旅行を探すなら目的別に選ぶのが正解
【マレット型パターの特徴と鉛の効果】
\自分でできる鉛調整/
パター用鉛

マレット型パターは、一般的なピン型に比べて重心が深く、慣性モーメントが大きいという特性があります。
そのためストローク中にフェースのブレが少なく、ミスに強い設計になっており、多くのアマチュアやツアープロに支持されています。
しかし一方で、ヘッドの重さに任せて振るとタッチが強く出すぎたり、狙いより右に出やすかったりといった声もあります。
そこで有効なのが「鉛調整」。鉛を貼ることで、ヘッドバランスや慣性モーメントを意図的にコントロールできるため、スイングテンポや打感の調整に活用されるのです。
マレット型はソール面積が広いため、トウ側・ヒール側・後方・上部など、鉛を貼れるポイントが多く、目的別に多彩な調整が可能です。初心者でも簡単に効果を実感できる点も魅力です。
マレットパターに鉛を貼る前に知っておくべきこと

鉛を貼ることでパターの挙動が変わる──これは確かな事実ですが、やみくもに貼ってしまうと逆効果になることもあります。
まず理解しておきたいのは、「鉛はフェースの開閉・重心位置・テンポ感に直接影響する」という点です。
たとえば、パターの重心がトウ側に偏るとフェースが閉じにくくなり、右に出やすくなります。
逆にヒール側に偏るとフェースが早く閉じて、引っ掛けが出やすくなります。
つまり、貼る位置によって打ち出し方向が変わるため、どこに・なぜ貼るのかを意識することが重要なのです。
鉛の重さにも注意!
また、鉛の「重さ」も意識すべきポイント。たった3gの差でもヘッドの挙動は大きく変わります。
最初は軽めの鉛(1g〜5g程度)からスタートし、自分のストロークに合わせて段階的に調整しましょう。
加えて、鉛の形状にも注目を。薄型シートタイプ、プレート型、貼り付け式ウェイトなどがありますが、シートタイプは微調整に適しており、初心者にも扱いやすいでしょう。
もうひとつ大事なのは、「鉛を貼ることはスイングのクセを隠す手段でもある」という点です。
もし「真っ直ぐ打てない」などの根本的な問題がある場合、鉛で矯正するよりも、まずストロークの見直しも検討すべきです。
これらを踏まえたうえで、自分に合った貼り方を見つけていくのが、鉛調整成功のカギとなります。
【基本編】マレット型パターの鉛の貼り方と位置のコツ
マレット型パターの鉛調整は、貼る位置によって得られる効果がまったく異なります。
ここでは、目的別におすすめの貼り方を具体的に紹介します。
ソール全面に貼る方法

ソール全体に鉛を貼ることで、ヘッド全体の重量が増し、ストローク時の安定感が向上します。
特に、インパクト時にヘッドがブレやすい場合や、重いグリーンでボールの転がりを良くしたいときに有効です。
また、全面貼りは座りの悪さを軽減し、構えた際の安定感も高められる点がメリットです。
フェース側(前部)に貼る方法

ソール前方(フェース寄り)に鉛を貼ると、重心が浅くなり、ボールを押し出す感覚が強まりやすくなります。
短い距離を確実に寄せたいときや、転がりが弱く感じる場合に効果的です。ただし、貼りすぎるとヘッドが前傾し、ストロークバランスを崩す可能性があるため、適量を守ることが重要です。
ソール後方に貼る方法

ソール後方への鉛貼りは、重心を深くして打点の安定性を高めます。
ミスヒットが多い方や、ロングパットで転がりを安定させたい場合に適しています。
深重心化により順回転がかかりやすくなるため、ボールがしっかりとカップまで届く効果も期待できます。
調整の基本は「貼る→打つ→確認→微調整」です。一度に貼りすぎず、少しずつ感触を確かめながら進めるのが、鉛調整を成功させる最短ルートといえるでしょう。
パターに鉛を貼るのはルール違反?知っておきたい規則と注意点
鉛を貼る行為自体はルール違反ではない
ゴルフクラブに鉛を貼って重量やバランスを調整することは、ゴルフ規則上認められています。パターの打感やストローク安定性を向上させるため、多くのゴルファーが活用している調整方法です。
プレイ中の調整はルール違反
注意すべきなのは、ラウンド中に鉛を意図的に追加・取り外しする行為です。これはクラブの性能を変更する行為とみなされ、ルール違反となります。調整は必ずスタート前に済ませておきましょう。
プレイ中に鉛が剥がれた場合の対応
ゴルフダイジェスト・オンラインによれば、ラウンド中に鉛が自然に剥がれてしまった場合は、そのままプレーを続けても問題ありません。また、同じ鉛を貼り直すことも許可されています。
フェースへの貼り付けは禁止
クラブフェース(打球面)に鉛を貼ることはゴルフ規則で禁止されています。これは打球性能に大きな影響を与えるためで、違反するとペナルティの対象となります。
マナー面での配慮も重要
鉛を貼る作業は他のプレーヤーのプレー進行や集中を妨げないよう、必ずラウンド前に済ませましょう。また、プレー中に剥がれないよう、接着面をしっかり清掃するなどの工夫も大切です。
貼りすぎには注意
鉛を過剰に貼るとパターのバランスが崩れ、かえって距離感や方向性に悪影響を及ぼす場合があります。ラウンド投入前に十分な練習でフィーリングを確認することが推奨されます。
【比較】ピン型・2ボールパターとの鉛の貼り方の違い

パターに鉛を貼るといっても、その貼り方はパターの形状によって大きく変わります。
マレット型とピン型、2ボール型では、重心設計やフェースバランスが異なるため、効果的な鉛の貼り方も異なるのです。
ピン型パター
まず「ピン型パター」の場合、トウ側が重くなりやすい設計になっています。
そのため、ミスの傾向として「引っ掛け」が出やすいプレーヤーは、ヒール側に鉛を貼ってフェースの閉じすぎを抑えるのが効果的です。
また、芯を外すと打感や方向性がズレやすいため、鉛でバランスをとることでミスの許容度を高める狙いがあります。
2ボールパター
一方、「2ボールパター」はその名の通り、ヘッド後方に丸い2つのディスクが配置されているマレットの一種です。
慣性モーメントが非常に高いため、ストロークの安定性は抜群ですが、そのぶん繊細なタッチの調整が難しいという面もあります。
このタイプではヘッド後方中央に鉛を貼ることで、さらに直進性を高めたり、タッチを重くする調整が一般的です。
マレット型パター
そして「マレット型パター」は、ピン型や2ボールよりも重心コントロールの自由度が高いのが特徴です。
ヒール・トウ・後方・上部など、広いソール面を使って多様な貼り方が可能です。
そのため、自分のストロークタイプや悩みに合わせて、カスタマイズ性の高い調整ができるのが強みです。
また、ピン型は「フェースバランスではない」モデルが多いですが、マレット型や2ボールはフェースバランス設計が主流です。
そのため、マレット型では鉛の位置で「フェースの開閉のしやすさ」も微調整できる点が、調整の面白さでもあります。
パターの形状によって鉛の貼り方も戦略が異なることを理解すれば、自分にとって最適なフィーリングを得るための第一歩になるでしょう。
【プロ実践】ツアープロはパターに鉛をどう貼っているのか?

パターに鉛を貼っているのは、何もアマチュアゴルファーだけではありません。
実は多くのツアープロも、繊細なフィーリングやコースコンディションに対応するために鉛を活用しています。
たとえば、オデッセイやスコッティ・キャメロンのパターでは、ソールに専用のウェイトポートが備わっており、
プロの多くはここに着脱式の鉛プレートを入れ替えることで、状況に応じた重量調整を行っています。
10g前後のウェイトをヒール側・トウ側に分散することで、打点の安定性やストロークのテンポを細かくコントロールしているのです。
実際に海外ツアーで活躍するプロの中には、「朝と午後でグリーンスピードが違うから鉛を貼り替える」という選手もいます。
ラウンドごとに鉛を使ってフィーリングを微調整するのは、プロならではの感覚へのこだわりといえるでしょう。
また、プロが鉛を貼る場所としては、やはり「ソールのヒール・トウ」が主流です。
左右のバランスを調整することで、ミスヒット時の転がりの安定感を高めたり、フェースの開閉を抑制しています。
さらに、シャフトの中間部やグリップ下に細く巻いた鉛を仕込むことで、手元重心に寄せる調整も行われています。
これはストローク中のヘッドの効きすぎを防ぎ、スムーズなテンポを生むのに役立ちます。
一見すると「プロの繊細すぎる世界」と感じるかもしれませんが、実はこの調整法はアマチュアにも十分応用可能です。
手軽に使える鉛シートや着脱式ウェイトが市販されている現在、プロの真似をすることで、
パターのフィーリングが格段に変わることを実感できるはずです。
パターの鉛で「引っ掛け」や「右に出る」悩みは改善できる?

パターの悩みで多いのが、「引っ掛けて左にミスする」あるいは「右にプッシュしてしまう」といった打ち出し方向のズレ。
これらはスイングのクセによる影響が大きいものの、鉛の貼り方でもある程度補正することが可能です。
まず「引っ掛け」の場合、多くはインパクト時にフェースが過度に閉じることが原因です。
この場合、ソールのヒール側(フェース寄りの根本側)に鉛を貼ることで、フェースが閉じる動きを抑制できます。
また、鉛を貼ることでヘッド全体の慣性が増し、ストロークがゆったりと安定するため、自然とスムーズな動きにもつながります。
一方で、「右に出る」ケースはフェースが開いたまま当たってしまう、またはインパクトで押し出してしまうのが主な原因です。
この場合は、トウ側に鉛を貼ることでフェースの閉じやすさを高め、打ち出しの方向修正に役立ちます。
さらに、ヘッドの上部(トップブレード)に貼ることで重心が上がり、フェースローテーションを促す効果も期待できます。
ただし、これらの貼り方はあくまでも応急的な矯正であり、根本的にはストロークの安定性を見直すことが最優先です。
たとえば、右に出るミスが頻繁に出る方は、構えがオープンになっていないか、目線が右を向いていないかなどのチェックも大切です。
鉛調整のメリットは、数グラムでフィーリングがガラリと変わる手軽さにあります。
貼る位置を変えるだけでストロークが安定することも多く、練習場やラウンド前に調整して効果を試せる点も魅力です。
「ミスの方向が毎回同じ」という方は、ぜひ鉛の貼り方での補正を試してみてください。パター本来の性能を引き出し、自信を持って打てるようになるはずです。
【実践レビュー】シャフトに鉛を貼った場合の変化とは?

パターに鉛を貼るというと、一般的にはヘッド部分への調整を思い浮かべる方が多いですが、実は「シャフトに鉛を貼る」ことで得られる効果も見逃せません。
特に、ストロークテンポや打感に違和感を感じている方におすすめの調整です。
まず、シャフトに鉛を貼る最大のメリットは、全体のバランスを“手元寄り”に変更できるという点です。
特に中間〜グリップ下に3g〜5g程度の鉛を貼ると、手元が重く感じられるようになり、結果としてヘッドの動きが安定し、テンポの乱れや“ヘッドの走りすぎ”を抑える効果が期待できます。
筆者の実践例では、ヘッドが効きすぎてパンチ気味になるクセを持っていたため、シャフトの中間(ちょうど左手下あたり)に2gの鉛を巻きつけたところ、明らかにストロークのリズムが落ち着き、余計な力みが減ったことでミスヒットも少なくなりました。
また、グリップ下部に鉛を貼ると、手元の重さが強調され、スイングの安定性が向上します。
これは、手首の余計な動きを防ぎ、肩の回転でストロークしやすくなるためです。
ただし注意点として、貼りすぎはNGです。
ヘッドの軽さを感じすぎて「打ち負ける感覚」や「タッチが届かない」といった違和感につながる場合もあります。
そのため、最初は1g〜2gの極小単位で試し、少しずつ調整するのがベストです。
貼る位置については、シャフトの側面よりも背面(目立たない側)に貼ると、構えた際の違和感も少なく済みます。
また、グリップを交換する予定があるなら、鉛をグリップ内に仕込む「鉛棒タイプ」もおすすめです。
シャフト調整は“隠れたテクニック”とも言える方法ですが、振りやすさ・タッチ・テンポ感の改善には非常に効果的です。パターのフィーリングに悩んでいる方は、ぜひ一度試してみてください。
【鉛の重さ選び|「何グラム」が適量なのか?】

パターに鉛を貼る際、多くのゴルファーが迷うのが「どれくらいの重さを貼れば良いのか?」という点です。
実は、この「重さの選定」こそが鉛調整の成否を大きく左右します。
結論から言えば、鉛の重さは使用者のレベルや目的によって変わるのが正解です。
初心者や鉛調整が初めての方は、まずは3g以下の軽量タイプから始めるのが基本。
少量でも、貼る位置によって打感やヘッドの挙動が大きく変化するため、まずは“変化を感じる”ことが最初のステップです。
上級者やフィーリングにこだわる方であれば、1g単位での貼り足し・貼り替えを行いながら微調整していくのが一般的です。
実際、多くのツアープロも1g〜5g単位でバランスを調整しており、貼る位置ごとに「感触の違い」を確認しながら、最適なセッティングを導き出しています。
10g以上の鉛を貼るケースもありますが、この場合は“明確な重みの変化”を意図した調整であることが多く、感覚が大きく変わるため、中級者以上やしっかり振りたい人向けといえるでしょう。
また、注意しておきたいのは「合計重量の増加が振り心地に及ぼす影響」です。
パターの標準重量は500〜550g程度が一般的ですが、鉛を貼ることでこれが560g以上になると、ストローク中に“重だるさ”を感じてしまう可能性があります。
貼りすぎはかえってフィーリングを損ねる要因になるので要注意です。
おすすめは「貼ったら5球打つ→違和感がなければそのまま→違和感があれば位置か量を変更」のサイクルです。
また、2〜3gずつ、複数カ所に分散させる貼り方も、重量感を保ちながら違和感を減らすうえで有効です。
鉛は“貼ってからが本番”です。何グラムが正解かは人それぞれ異なりますので、少量から試して、自分の感覚に合った重さを見つけていくことが、理想のタッチへ近づく近道になります。
おすすめの鉛シート・パター用ウェイトアイテム
パターの鉛調整をする際に欠かせないのが、扱いやすく信頼性の高い鉛シートやウェイトアイテムです。
最近ではゴルフ専用として販売されている製品も増えており、用途や目的に応じて選ぶことができます。
まず初心者におすすめなのが、「鉛シートタイプ」の製品です。
薄くて柔らかく、ハサミで簡単にカットできるため、1g単位の微調整がしやすいのが特長です。
特にタイトリストやミズノから出ているゴルフ用鉛シートは、接着力が強く、ラウンド中に剥がれにくいと評判です。
Amazonや楽天でも手軽に購入でき、価格も500円〜1,000円前後とリーズナブルです。
よりしっかりとした重量感を求める中級者〜上級者には、「プレート型ウェイト」も選択肢に入ります。
これはマレット型やオデッセイ、スコッティ・キャメロンなどの特定モデル専用のウェイトユニットで、ネジ式で着脱できるため、見た目を損なわずにバランス調整できるのが魅力です。
加えて、シャフト用の「鉛テープ」も販売されています。
これは細長い棒状またはロール状の鉛で、シャフトの中間やグリップ下に巻きつけるタイプ。
ストロークテンポやフィーリングに変化をつけたい方にぴったりのアイテムです。
その他、ゴルフ5やヴィクトリアなどの店舗では「パター調整キット」として、シート・テープ・プレートがセットになった商品も販売されており、これを使えば複数パターへのセッティング比較も可能です。
もし鉛の見た目が気になる方には、黒色やグレーの“目立ちにくいカラー仕様”の鉛もあります。
こうしたタイプは、構えたときの違和感を最小限に抑えることができるため、感覚重視のゴルファーにも人気です。
まとめると、
・初心者:シートタイプ(細かい調整がしやすく、安価)
・中上級者:プレート型・シャフト用(見た目・重量感を両立)
という基準で選べば、失敗が少なく、パター本来の性能を最大限に引き出せるでしょう。
【まとめ】鉛の貼り方でマレットパターの性能は激変する!

ここまで解説してきたように、マレット型パターにおける鉛の貼り方は、ストロークの安定性・打ち出しの方向性・フィーリングに至るまで、あらゆる面に影響を与えます。
とくにマレット型は、ソール面積が広く重心位置の自由度が高いため、「どこに貼るか」によって得られる効果がまったく異なるのが特徴です。
後方に貼れば慣性モーメントが増して直進性が向上し、トウ・ヒールに貼れば引っ掛けや右プッシュの矯正に効果を発揮します。
また、プロの世界ではごく当たり前のように鉛調整が行われており、10g前後を貼り替えてグリーンスピードやコンディションに対応しています。
このような微調整は、アマチュアにも十分再現可能であり、実際に「鉛を貼っただけで3パットが激減した」という声も多数あります。
重要なのは、貼る位置や重さをやみくもに決めるのではなく、自分の悩みや目的に応じて「まず試す → 少し打つ → 様子を見る →微調整する」このサイクルを丁寧に行うことです。
また、貼る量も一度に10gなどと極端にするのではなく、1g〜3g程度の軽量から始め、複数箇所に分けて貼ることでバランスを崩さずに感覚を掴みやすくなります。
さらに、シャフトやグリップ下に鉛を使うことで手元重心を高め、ストロークテンポを整えるという調整法もあります。
これは振り遅れや打ち急ぎに悩む方に効果的なアプローチです。
市販の鉛シートやウェイトは、手頃な価格で導入でき、初心者でもすぐに始められるのが魅力です。
「パターがなんとなく合わない」「距離感が安定しない」という方は、まず鉛を試すだけで、驚くほど改善する可能性があります。
ぜひあなたも、パターに鉛を貼ることで“自分だけのベストセッティング”を見つけてみてください。スコアアップへの近道が、意外とすぐそこにあるかもしれません。
✅【記事まとめ】

- マレット型パターは重心が深く、鉛調整による変化が大きい
- 鉛は打感や方向性、ストロークの安定性に影響を与える
- ソールのヒール・トウ・後方など貼る位置で効果が異なる
- ピン型や2ボールパターと貼り方の戦略が違う
- ツアープロは1g単位で鉛を貼り分け、感覚を調整している
- 引っ掛けにはヒール側、右に出るならトウ側への貼り付けが有効
- シャフトに貼ることでストロークテンポや手元バランスを調整できる
- 鉛は3〜5gの軽量から始め、少しずつ増やすのが基本
- 鉛シートや着脱ウェイトなど市販アイテムも充実
- 貼る→打つ→確認→微調整の流れで、自分だけの最適バランスを見つける
【PR】気づいた人から使っている!しゅうごる部で話題沸騰中の人気ゴルフアイテム
ここからは、しゅうごる部で実際に選ばれ、売れている注目アイテムを厳選してご紹介します。
スコアアップや快適さにつながると評判のアイテムばかりなので、今のゴルフに何か足したい方にぴったりです。
話題になる理由がわかるラインナップを、ぜひチェックしてみてください。
自宅で距離感を鍛えるパターマット|プレミアムプレッシャートレーナー
完璧な距離感を身につけたい方に選ばれている、話題のパタートレーニング器具です。
カップインの強さが合わないと戻ってくる構造で、自然とタッチの精度が磨かれます。
自宅練習でも実戦に近い緊張感があり、ショートパットの安定感を高めたい方に最適です。
ショートパットを徹底的に安定させたい方へ|SUPER-BENT スーパーベントパターマット
日本製ならではの精密な仕上がりで、本芝に近い転がりを自宅で再現できるショートパット専用マットです。
45cm×2.2mの実戦的な長さに、距離感を磨けるマスターカップ付きで、カップイン率の向上に直結します。
方向性とタッチを同時に鍛えたい方や、パターの基礎を固めたい方に選ばれている定番モデルです。
自宅で本格スイング練習ができる大型スイングマット
屋外に行かなくても、実際のコースに近い感覚でスイング練習ができる自宅用スイングマットです。
高低差のある2種類の芝と厚みのある設計で、足元の安定感とインパクト時の感触をしっかり再現。
フルスイングの確認や体重移動の練習まで行いたい方に適した、本格派トレーニングマットです。
冬ゴルフでも冷えに負けないハンドウォーマー付き防寒グローブ
寒さの厳しい日のラウンドや練習でも、手先の冷えをしっかりガードして快適にプレーしたい方におすすめの防寒グローブです。
内側の高密度フリースが優れた保温性を発揮し、指先まで暖かさをキープしつつ、クラブ操作の自由度やグリップ感もしっかり確保します。
冬季のスコア安定や集中力維持に役立つ、ゴルファーの強い味方アイテムです。
風を防いで快適にプレーできる ピンの長袖ウインドブレーカー
ピンの長袖ウインドブレーカーは、冷たい風をしっかり防ぎながら、動きやすさにも配慮された実用性の高い一着です。
軽量な素材を使用しているため、スイング時の違和感が少なく、ラウンド中の体温低下を抑えやすいのが特徴。
朝夕の肌寒い時間帯や、風が強い日のラウンドでも快適な着心地を保てます。
シンプルで落ち着いたデザインなので、年齢やスタイルを選ばず、練習場からコースまで幅広く使えるゴルフウェアです。
眠っていた代謝を呼び覚ますヒートラップ
着るだけで体の熱を外に逃がしにくくし、自然な発汗環境をつくるサウナシャツ。
ポリマー2重構造が体温を効率よくキープし、自宅時間や移動中など「スイングしていない時間」もムダにしません。
動きを妨げない伸縮性と軽さで、日常生活に溶け込む着用感を実現しています。
ラウンド後やオフの日でも体を意識したケアをしたい、30代から50代のゴルファーにこそ試してほしい一枚です。
ゴルファーの毎日を支える24時間リカバリーウェア ReD
リカバリーウェア ReDは血行促進によって肩こり改善と疲労回復をサポートするインナーです。
スイングで負担がかかりやすい肩や首まわりをケアして、ラウンド後のコンディション調整に役立ちます。
Vネック仕様の半袖インナーのため練習時や移動中でも着用しやすく普段使いにもなじみます。
ゴルフを長く楽しみたい男性が日常的に体のケアを意識するための一枚です。
プロや上級者も注目!体の軸を支えるコアフォース
コアフォースは、身につけることで体の軸やバランス感覚を整えやすくし、スイングや動作の安定感をサポートしてくれるアクセサリーです。
ゴルフでは体幹が安定しやすくなることで、アドレスやトップの再現性が高まり、「振りやすい」「力まずに打てる」と感じる人も少なくありません。
また、首元や手首まわりに自然になじむデザインで、ラウンド中だけでなく普段使いしやすいのも特徴です。
長さやカラーのバリエーションが豊富なので、体格や好みに合わせて選びやすく、ゴルフ好きな方へのプレゼントとしても非常に喜ばれやすいアイテムです。
軽さと収納力を両立した 8本収納ゴルフバッグ パイクスピーク
必要なクラブだけをスマートに持ち運べる、8本収納対応の超軽量ゴルフバッグです。
練習場やショートコース、セルフ練習に最適なサイズ感で、肩掛けしやすく移動も快適。
大容量設計と3年安心保証付きで、実用性と安心感を兼ね備えた一本です。
ミニマルデザインで差がつく 9インチスタンドキャディバッグ
無駄を削ぎ落とした洗練デザインが魅力の9インチスタンドキャディバッグです。
軽量設計ながら収納力もしっかり確保されており、練習からラウンドまで幅広く対応します。
落ち着いたカラーと上質な素材感で、シンプル志向のゴルファーにぴったりの一本です。
大人ゴルファーのための限定キャディバッグ
人と同じキャディバッグでは満足できないゴルファーに向けた、強い個性を持つモデルです。
アンティーク調のデザインは、派手さで目立つタイプではなく、落ち着いた雰囲気の中でさりげなく違いを演出したい大人ゴルファーに最適です。
大量生産の無難なバッグではなく、数量限定ならではの特別感や所有する満足感を重視する人にとって、このキャディバッグは「長く使いたくなる相棒」になります。
上質感のあるデザインで、ゴルフ場でも大人らしい雰囲気を演出したい方に
上質な素材と上品な光沢を備えた「DICROS SOLO Series」の大容量カートトートバッグ。
ディクロスソロ素材の美しい奥行きと透明感が、ゴルフラウンドでも洗練された存在感を演出します。
ボトルや大きめの水筒、氷嚢など荷物が多いラウンドでも余裕で収納できる大きめサイズで、カートへの載せやすさを考えた底幅設計と、持ち手の長さを調整して肩掛けもできる機能性を両立しています。
カジュアルなラウンドだけでなく普段使いでも映えるデザインは、機能性とスタイルを同時に求めるゴルファーの毎日に寄り添います。
初心者も安心 バッグが選べるワールドイーグル14点フルセット
これからゴルフを始める方にぴったりの、クラブからキャディバッグまで揃ったオールインワンセットです。
ドライバーからパターまで実戦で使える14点構成で、買い足し不要ですぐにラウンドへ行けます。
バッグは複数カラーから選べるため、機能性だけでなく見た目にもこだわりたい方におすすめです。
高初速と直進性を両立する Qi35 ドライバー
Qi35 ドライバーは、ヘッドスピードに自信がないゴルファーでも扱いやすい設計を追求した現代的なゴルフドライバーです。
軽量シャフトと最適バランスのヘッド設計が、初速の出しやすさと直進性の高さを両立し、飛距離アップに貢献します。
初心者から中級者まで幅広い層にマッチし、ラウンドでの信頼感を高めてくれる一本です。
叩いても吹けない強弾道!スリクソン ZX7 Mk II ドライバー
ダンロップ スリクソン ZX7 Mk II ドライバーは、低スピン設計による強い弾道と高い操作性を追求したツアー志向モデルです。
リバウンドフレーム構造により、芯で捉えたときの初速性能が高く、叩いても吹け上がりにくいのが特長です。
コンパクトなヘッド形状と調整機能により、フェードやドローを打ち分けたい中上級者の要求にしっかり応えます。
安定感よりも球質とコントロール性を重視するゴルファーに最適な一本です。
フェアウェイウッドが上手く当たらず、距離と方向性の両立に悩んでいる方に
ワークスゴルフと三菱ケミカルが共同開発した「ワークテック飛匠」シャフトを装着したフェアウェイウッドで、しなやかな先中調子が心地よい振り抜きを演出しつつ飛距離と操作性のバランスを高めます。
直進性を重視したヘッド設計と安定した弾道で、スライスを抑えつつ狙ったフェアウェイに強い弾道で飛ばせる性能を実感できます。
初中級者から中上級者まで扱いやすさとコスパの良さを両立し、ワンランク上の飛びを追求するゴルファーに最適な一本です。
XXIO ゼクシオ 14 レディース フェアウェイウッド
\ミスヒット時でも安定した飛び/
ゼクシオ14レディース

ゼクシオ14レディース フェアウェイウッドは、力に自信がない女性でも楽に振れて高く飛ばせるやさしさを追求したクラブです。
軽量設計と最適化された重心設計により、フェアウェイやラフからでもボールを拾いやすく、安定した弾道を打ちやすくなっています。
ミスヒット時でも飛距離のロスが少ないため、フェアウェイウッドが苦手な初心者からスコアアップを目指す中級者まで幅広く対応します。
振り抜きやすさと安心感を重視し、セカンドショットで確実に距離を稼ぎたい女性ゴルファーに選ばれている一本です。
アプローチで差をつけたいゴルファーにピン S259 ウェッジ
ピン S259 ウェッジは、悪条件でも安定したスピン性能を発揮する、ショートゲーム重視のゴルファー向けウェッジです。
新設計の溝構造とフェース処理により、ラフや濡れたライでもスピン量が落ちにくく、距離感を合わせやすいのが特長です。
複数のソールグラインドが用意されており、入射角やスイングタイプに合わせて最適なモデルを選べます。
アプローチとバンカーをスコアメイクの武器にしたいゴルファーに、特におすすめの一本です。
安定感と構えやすさを追求したAi-ONE トライビーム 2ボールCS パター
オデッセイの2025年モデル Ai-ONE トライビーム 2ボールCS パターは、高い直進性と安心感のある構えやすさが特徴のセンターシャフトパターです。
2ボールデザインによる視覚的なアライメント効果と、トライビーム構造によるヘッドの安定性が融合し、ストローク中のブレを抑制。
距離感と方向性の両立を重視した設計で、ショートパットの成功率を高めたいゴルファーに心強い1本です。
オデッセイ Ai-ONE SILVER SERIES #7 パター|安定した距離感と方向性を求める方へ
\安定した距離感と方向性/
Ai-ONE SILVER SERIES #7

オデッセイの Ai-ONE SILVER SERIES #7 パター は、視認性の高いアライメント設計と、重心バランスを追求したヘッド形状でショートゲームの安定感を高めるパターです。
スクエアに構えやすいデザインが、真っ直ぐ引きやすいストロークをサポートし、転がりの質と距離感の再現性を向上させます。
初心者はもちろん、アプローチの精度を高めたい中級者にもおすすめできる、信頼感のある一本です。
飛びとうれしさを両立する ブリヂストン レディースゴルフボール
ブリヂストンのレディースゴルフボールは、やさしい打ち出しと安定した飛距離、そして柔らかな打感をバランスよく実現したモデルです。
女性ゴルファーのヘッドスピードやスイング特性に合わせた設計で、高弾道と安心感ある飛びをサポートします。
コントロール性能と飛びの両立を目指す方や、ミスヒットでも距離ロスを抑えたいプレーヤーに選ばれている定番ボールです。
しゅうごる部の皆はどうしてる?単発レッスンはまず口コミをチェック
ゴルフが上達したいけれど、「どこでレッスンを受ければいいかわからない…」という人はとても多いですよね。
そんなときに役立つのが、全国のゴルフレッスン情報をまとめてチェックできるサイト、「ゴルフメドレー」です。
このサイトでは、全国の単発レッスン・短期レッスンなどを簡単に検索でき、実際に受けた人の口コミや評価も確認できます。
口コミや条件を見て、自分の予算やスケジュールに合うレッスンが見つかれば、体験レッスンを受けてみましょう。
行き詰まりを感じたら、プロのアドバイスを受けるのが最短のステップアップ!
まずは口コミで評判をチェックして、あなたにぴったりのゴルフレッスンを見つけてください!
▶レッスン検索はコチラ
ゴルフ旅行を探すなら目的別に選ぶのが正解
ゴルフ旅行は、プレー数や宿泊日数を柔軟に決めたい人と、宿泊そのものの満足度を重視したい人で、選ぶサービスが変わります。
ここでは、目的別に使い分けしやすい2つの人気サービスを紹介します。
プレー数・宿泊日数を自由に選びたい人におすすめ

プレー数や宿泊日数を自分の予定に合わせて細かく設定できるのが、J-TRIPゴルフツアーの強みです。
1ラウンドから複数ラウンドまで選択でき、出発地や日程、部屋タイプもまとめて検索可能。
「短期間でたくさん回りたい」「日程に制限がある」という人でも、無駄のないゴルフ旅行を組みやすいのが魅力です。
▶ プレー数・宿泊日数を自由に選ぶならコチラ
ワンランク上の滞在を楽しみたい人におすすめ

ゴルフだけでなく、宿泊の質や非日常感も重視したい人には、星野リゾート宿泊プランがおすすめです。
星野リゾートに宿泊しながらゴルフを楽しめるプランがまとまっており、リゾートステイとラウンドを同時に満喫できます。
記念日旅行や夫婦・友人とのご褒美ゴルフなど、「特別感」を求めるシーンに最適です。
▶ 星野リゾートに宿泊してゴルフを楽しむならコチラ